
ここは、富士山の女神を祭る浅間大社の奥宮。そう、とても神聖な場所なのです。
急な道、長い道、つらい道、どの登山道から登っても、行き着くところは一緒だよ、
とやさしく語りかけてくれてくれているよう。気力・体力があり、かつ天候に恵まれたら、
ぜひ歩いてみてください。富士山周辺の大パノラマが最高です。
火口の直径は久須志神社から富士山測候所まで780m、
火口の深さは200m以上あります。歩行距離は3キロ。
平均的な脚力で1時間半ぐらいかかります。
なお、強風などの悪天候の場合は中止するべきであることは言うまでもありません。
なにせ、外側は崖、内側は火口。吹き飛ばされたらアウトです。
基本的には時計回りですが、馬の背という剣が峰への急斜面を
登らなくて良いということで左回りを選ぶ方もいます。
トイレは2カ所あります。
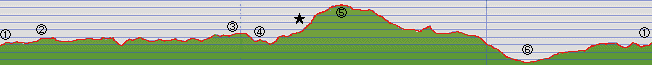
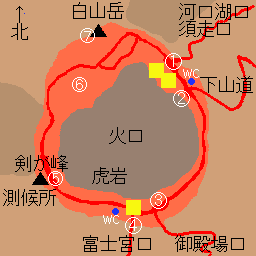
(1):久須志神社、そして4軒の山小屋が並んでいます。
(2):大日岳 ご来光を見るのに最高の場所とされています。
(3):銀明水 霊水がわきでる場所です。山小屋あり。
(4):浅間大社奥宮、郵便局、山小屋があります。
(5):剣が峰 ご存じ日本最高地点。
(6):火口棚
(7):釈迦の割石
富士山測候所のちょうど反対側です。多くのバスツアーではお鉢巡りをする時間がありませんので、
注意してください。
下図は、GPSによるお鉢巡りの高低差のグラフです。左図のとおりに(1)から時計回りで歩いています。
(★)の急な部分が馬の背です。逆に左回りですと(6)火口棚から(5)剣が峰まで、高低差80mの登りが続きます。
山頂の河口湖口、須走口側にあるのが久須志神社。富士山の八合目以上は富士山本宮浅間大社の
奥宮境内。つまり浅間大社の所有地なのです。
かつて徳川家康が、浅間大社による所有を認めた
ことに端を発しています。久須志神社には、
大名牟遅命、少彦名命が祭られています。
御来光が一番きれいに見えると言われる大日岳から見た河口湖口側の山小屋の風景です。
久須志神社は一番奥です。登山道はそこにつながっています。
そしてトイレ、下山道は手前右になります。山小屋が4軒。昼間はおみやげが売られ、
すっかり観光地の雰囲気です。御来光は右方向から登ってきます。
平安時代(9世紀)に登頂した都良香(みやこのよしか)の「富士山記」にも
この虎岩のことが「蹲虎(うずくまる虎)の如し」と記述されています。
火口底まで約200mの高低差があり、春頃にはスキーで滑走する人もいます。
アンビリーバブルです。滑ってから登ってくるのがものすごく大変だと思う。
金明水と並んで霊水とされる水がわきでるところ。
昔は貴重な飲料水として登山客に
ふるまわれていました。
山頂なのに地下水が湧き出るのはちょっと
不思議な感じがします。現在は囲われています。
ちょうどここが御殿場口のゴール地点。
富士宮口の山頂にある奥宮。
主祭神はコノハナサクヤ姫という美しく、
そして情熱的な性格の女神様。
古事記では夫のニニギノミコトに妊娠した
子供が本当に自分の子供なのかと疑われて、
それを証明するために産室に火をつけて
燃えさかる炎の中で出産したというからすさまじい。
ここで結婚式を挙げるカップルもいます。
参列者は大変です。70才以上の方が参拝記帳すると
記念品がいただけるそうです。
郵便局もここにあります。
剣が峰への最後の難所が馬の背。
砂礫の急斜面は滑りやすく登りにくいです。
これを避けるために左回りでお鉢巡りをする人も
いますが、「下るには急すぎるので、
やはり登る方が良い」「この急斜面を登らない
と登った気がしない」という意見も。
強風時は危険なので登るのは控えてください。
1964年(昭和39年)、東京オリンピックの年に
レーダードームが設置されましたが、
2001年に解体され富士吉田市の観光施設
に移築されました。
右の写真の左手前に富士山そのものでは一番高い場所(3776.2m)となる岩があります。
そこには赤いペンキで鳥居が描かれているのですぐわかりますが、
その岩に乗り出すと危ないので注意してください。測候所の脇には展望台があります。
とても素晴らしい眺望を楽しめますが、はしごが狭いので気をつけてください。
測候所から(6)の方向を見た写真。
白いものは電波望遠鏡です。
以前は外側から回り込む外輪コースと
火口近くを歩く内輪コースの2つのルートが
ありましたが、最近は外輪コースだけになっているようです。
山頂のお鉢の縁まで登るので、
大沢崩れを見下ろすことができます。
その後、火口棚まで下り、久須志神社、
河口湖口側の山小屋群へ到達します
(写真の右端あたり)。
再び50mほどの標高差を登るので、
けっこうしんどい場所です。
この地点には道が二つあります。
火口寄りの道を通ると「金明水」の碑を
見ることができます。
写真の右部分の高い場所が白山岳。
その角張った崖の部分が「釈迦の割石」という
風流な名前で呼ばれている部分です。
白山岳は昔、釈迦ガ岳と呼ばれていたので、
それで「釈迦の割石」と呼ぶのだと思います。
昔の絵葉書、登山案内では必ず、
この「釈迦の割石」が大きくとりあげられています。
お鉢めぐりの名所の一つでした。
外輪コースを雷岩(稜線の少し盛り上がった地点)を
経由して白山岳に向かって近づいていけば、
そびえ立つように迫ってくる偉容に感動できるの
だと思いますが、現在は危険なので通行禁止
になっています。
明治維新の廃仏毀釈で仏教色を廃するために改名されました。
古くは、山頂の8つの峰を「八葉蓮華」(お釈迦様が座っている蓮のことです)に例え、
その「八」から「おはちめぐり」と呼ばれたのだそうです。
その後、富士山の形が鉢のようであることから、お鉢めぐりとなりました。